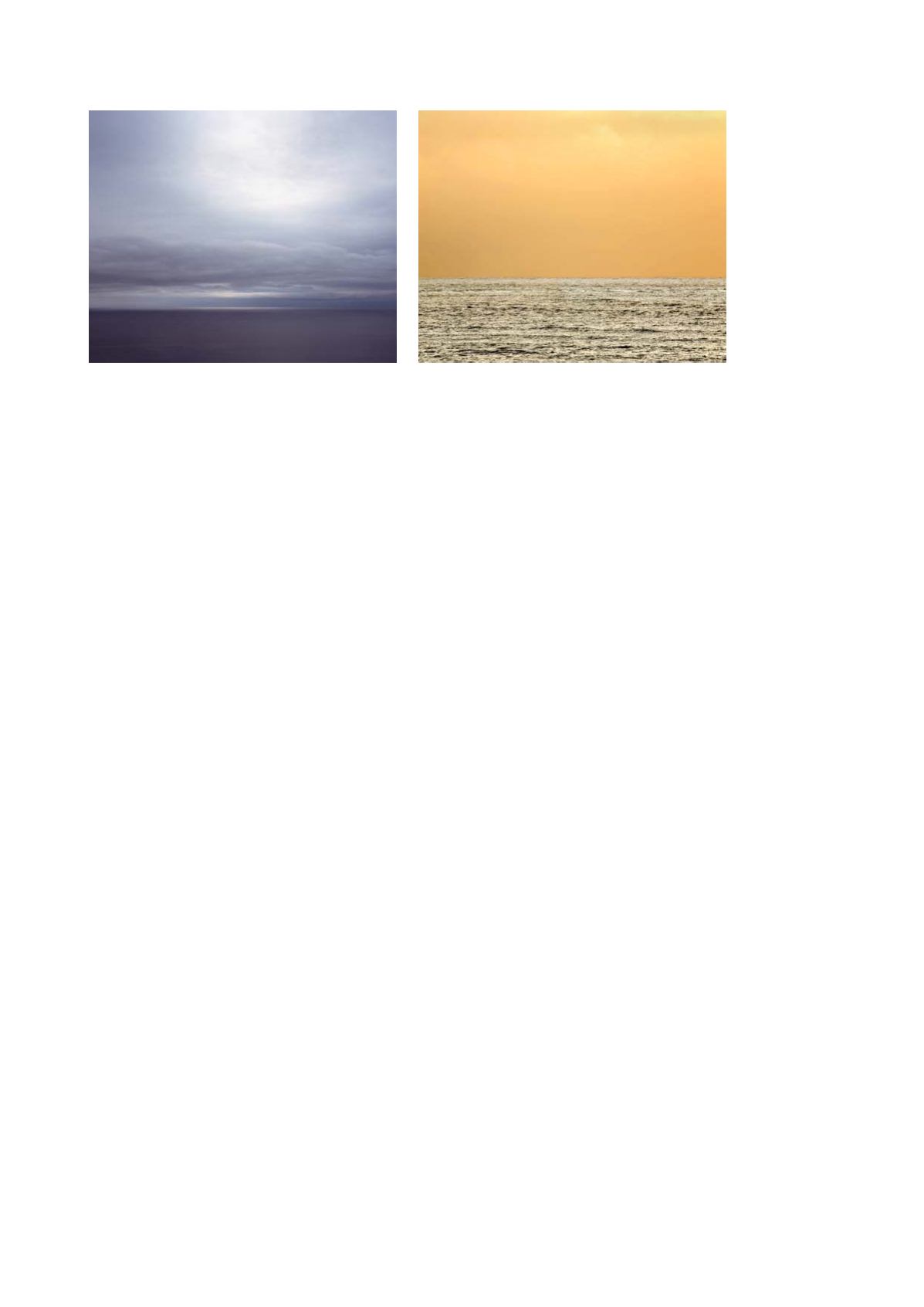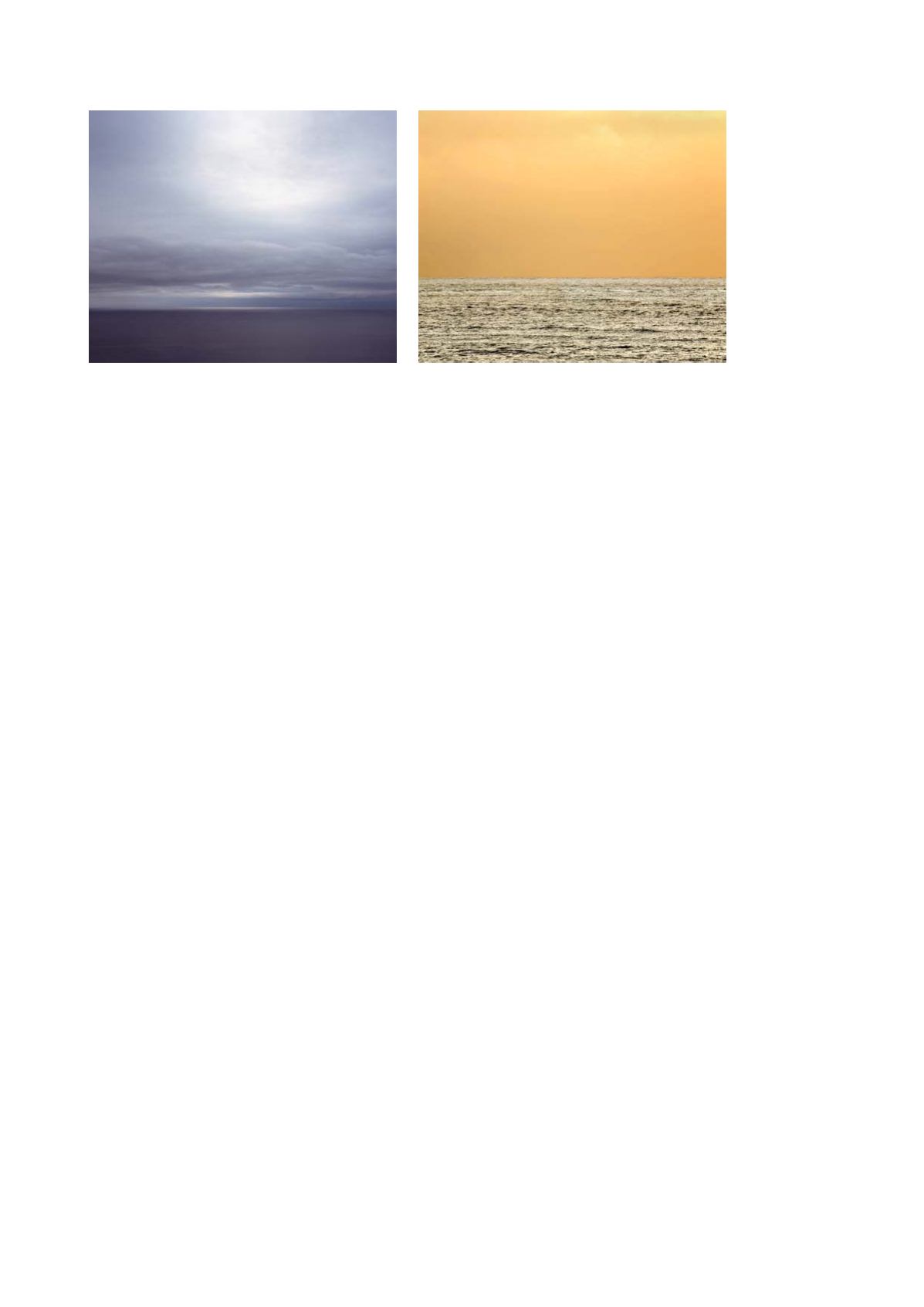
5
サークルを撮った「神々の故郷」シリーズでも使ってみた。「技術の恵み」シリーズ
で撮影した計器、機械、器具にも同様のことが言える。
つまり私の写真は、基本的には形を研究、観察し、これを精神的に深めることに
よりその意義を伝える手段である。この認識をつきつめてゆくと、「形」と「根底」と
を総合する心構えが求められる。これを無名に終わったフランスのある作家はLa
form e,c’estle fond,quirem onte a la surface(形とは表面へと持ち上げられた
根底である)という文で表現した。つまり私達は形から根底を推し量ろうというので
あり、その根底は、それぞれ際立った進歩を遂げた各時代が続いていった源で
あるかも知れないのである。ある意味で「作るという行為の普遍的意味を認識」
し、神の創造の神秘性を、作るという行為に置き換えようというのである。またして
も「方法は目的」なのである。啓蒙時代によって必然的に疑う気持ちが芽生え、
その結果神話は脇へ追いやられ、信仰が失われたが、これと並行して生きる意
味の探求や、「地球という体系」というはっきり感知できる構造の中で安心を求め
ることが始まった。特に進化をより深く理解することの中に、また地球及び人類の
歴史の中に、発達史に基づいた、形而上学的な、つまりもはや信仰だけを特徴
としなくなった世界観を考える当然のきっかけがあるのだと私は思う。
観察し、記録する機会がほとんど3000年にわたって存在していた地球及び人類
の歴史の様々なプロセス以外どこにも、「根底」は見つからないのである。
写真、特に顕微鏡写真と天体写真は、小宇宙及び大宇宙の構造を学ぶための
手段である。今日の技術水準では、写真は拡大してゆけば哲学と接する部分が
あるような認識に達することが予想されるところまで来ているので、やがては自然
科学と精神科学を融合させることができるかもしれない。
美的基礎
エックハルト・ショルマイヤーはその祝辞[8]の中で、私の芸術活動を西洋哲学と
銀の糸で結び付けた。そこで、以下の文は私のここで取り上げた作品の審美的
な面だけを取り上げるにとどめたいと思う。
私にとって美は全ての造形的なものの基本であり、従って私は写真では必ず美
的造形を心がけている。20世紀以降の美術の特徴は反審美の立場であり、これ
はおそらく社会の既成秩序の仕組みに疑問を投げかける試みにも表れている。
美的に完全な形も常に繰り返し使われると不快感を起こさせる既視感につなが
ることは間違いない。
しかし一方では時期を同じくして、あらゆる社会層に共通する明晰で理解できる
形による表現も生まれた。この表現は原形や単純なものの美の見直しという形を
とって現れている。バウハウス運動、マックス・ビル等のコンクリートアート、少し後
のドナルド・ジャッド、ソル・ルウィット、ロバート・マンゴールドのミニマル・アート、
また他の分野ではスカンジナビア諸国のデザイナー達が数世代にわたってこの
動きに寄与してきた。こうした形はそれを全体として、あるいは個々の要素として
9 -
海の静けさ, FH 001
10 -水平線 12, FH 086